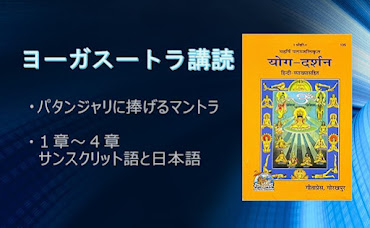वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात्सम्प्रज्ञात:॥17॥
ヴィタルカヴィチャーラーナンダースミターヌガマート
サンプラジュニャータハ
संम्प्रज्ञात: サンプラジュニャータハ
有想三昧とは
वितर्कविचारानन्दास्मितानुगमात् ヴィタルカヴィチャーラーナンダースミターヌガマート
尋(ウ゛ィタルカ)、伺(ウ゛ィチャーラー)、楽(アーナンダ)、我想(アスミター)を伴った三昧である。
長くて読みにくいシュローカですが、古代人が単語の前後を繋げ暗記をしやすくしたので、それを解凍してひとつひとつの単語と全体の意味を把握していきましょう。
・वितर्क ヴィタルカ
尋(じん)。
物質的な粗雑な対象に対して起こる段階の三昧。
物事に対し、また、起こっている事象に対して知ろうとしている段階。分析。
サヴィタルカ と ニルヴィタルカに分類されます。
सवितर्क サヴィタルカ
有尋定。集中している対象の言葉、意味、知識のイメージや分析を伴う段階におこる三昧で、それを有尋定(サウ゛ィタルカ)という。
निर्वितर्क ニルヴィタルカ 無尋定
有尋定からさらに前進して、言葉、意味、知識についてのイメージや分析がなくなり、より一体となったとき、それを無尋定(ニルヴィタルカ)という。
・विचार ヴィチャーラ
伺(し)。
集中している対象物に対する、より微細で本質的なところに対して、感覚器官と心の内奥(三内宮・・・覚、慢、意)が働き、伴う三昧。
手前のヴィタルカの段階で、物事を分析した結果、より微細な思考と、そこから取捨選択したり、自分なりに答えを出そうとしている段階。
サヴィチャーラ と ニルヴィチャーラに分類されます。
सविचार サヴィチャーラ
有伺定。
言葉、意味、知識のイメージや分析が伴う。
निर्विचार ニルヴィチャーラ
無伺定。
有伺定から前進して、言葉、意味、知識からくる分析やイメージを伴わない三昧。
【補足】
サヴィタルカとサヴィチャーラを併せて、仏教用語で「有尋有伺 (うじんうし)」
ニルヴィタルカとニルヴィチャーラを併せて「無尋無伺(むじんむし)」
と呼びます。
・आनंद/आनन्द アーナンダ
ひとことで「楽」という訳がよくありますが、快楽や感覚器官を伴う喜び、外界からくる楽しさという意味があります。
このほか、アハンカーラ(अहंकार)とよばれる我意識・自惚れの意味も含まれます。
ヴィタルカ、ヴィチャーラーの三昧のステージをこえたところに、次はアーナンダが伴う三昧のステージをいいます。
・अस्मिता アスミター
我想。
自己同一性、私という意識。エゴの根本。
アスミターは、夢の幻影であるマーヤーの世界を見ている私という、最も原始的な私という存在であり、この我想という存在が、自己と他者を区別する始まりとされます。
ここでは、ヴィタルカ、ヴィチャーラとアーナンダが伴わない次の段階の三昧がアスミターを伴う三昧で、これも有想三昧の中では最も高度な三昧です。
【補足】
有想三昧の類義語として、有種子三昧
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषो ऽन्य:॥18॥
ヴィラーマプラティヤヤービャーサプールヴァハ
サンスカーラ シェーショーアンャハ
・अन्य: アンヤハ
もうひとつのサマーディは(無想三昧について)
・विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: ヴィラーマプラティヤヤービャーサプールヴァハ
心の活動を止める想念を修習した結果生じる境地で
・संस्कार शेष: サンスカーラ シェーシャハ
サンスカーラだけがのこっている状態
*今世におよぶ前世からの行為の影響
*今世におよぶ前世からの行為の影響
・अभ्यास アビャーサ
修習、練習
無想三昧は、打ち消しの意味を伴う「ア」をつけて、
असंप्रज्ञात योग (समाधि) アサンプラジュニャータ ヨーガ (サマーディ)
といい、
この無想三昧と同じ意味を有する同義語として
この無想三昧と同じ意味を有する同義語として
निर्बीज समाधि ニルビージャ サマーディ
無種子三昧
無種子三昧
कैवल्य カェヴァルヤ
独存
ともいいます。
【 ज्ञの文字と発音】
ज्ञ という文字は正当なサンスクリット語では「ジュニャ」と発音するのが正しく、現代ヒンディ語では「ギャ」と発音します。
「知識のヨガ」とよばれる「ज्ञान योग」のことを古典的な書物を読む時は「ジュニャーナ ヨーガ」とよぶほうが正統でしょう。スートラのインド人の発音を聞いてみると「ニャ」と聞こえて、「ジュ」はほとんど聞き取れないものもあります。
ところが、現代ヒンディ語でも立派に生きている単語なので「ギャーン ヨーガ(ヨーグ)」と言うインド人も実際のところ多いです。(単語の末尾は子音字のみ発音するのがヒンディ語の規則なので読みはギャーナではなく、ギャーンになります。外国人が比較的少ないウッタラカシというエリアに行くと、YOGAと言うと通じず、YOGと発音すると通じることがありました。)
こういうわけで、私も日常ヒンディ語を使うので「ギャ」を使う習慣がついてしまい、この講読では、ギャと書いたり、ジュニャと書いたりすることもあります。度々統一されていないことを、ご承知ください。