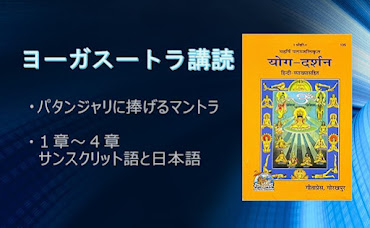この6つの浄化法は英語では「シックス ボディ クレンジング プロセス」とも呼ばれます。普段私たちが見慣れている日常的な行法もありますが、独特な行法の中には身体レベルの他プラーナーヤーマが熟達していなければできないものもあり、必ず師から学ぶ必要があります。
浄化法の目的やベネフィットも抑えておきましょう。
●トリドーシャ(ヴァータवात、ピッタ पित्त、カファकफ) のバランスが調整されることで身体と心のバランスを整える。
●身体の内部から長年蓄積した不純物、未消化のものを出し切り、消化器系、循環器系、呼吸器系が強化されることにより、病気の改善や予防を目指す。
●ヨーガのプラクティスが向上する。
浄化法は大別すると6種類で、個々のシャトカルマに対しさらなる分類が意外と多く、同義語の名称が多くあったり、分類の仕方が講師によって多々異なることがあります。できるだけ整理したうえで要点をまとめていきます。
まず、シャトカルマについては、以下の2大古典書の中に記されています。
・ゲーランダ サンヒター(घेरण्ड संहिता)
・ハタヨーガプラディーピカー(हठयोग प्रदीपिका )
ハタヨーガプラディーピカーは、著者スワートマーラーマによって記されたハタヨーガの代表的な経典のひとつで、2章22節に記されています。
ハタヨーガプラディーピカーは、著者スワートマーラーマによって記されたハタヨーガの代表的な経典のひとつで、2章22節に記されています。
またゲーランダ サンヒターでは1章12節の中で述べられています。
धौतिर्बस्तिस्तथा नेतिस्त्राटकं नौलिकं तथा।
कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते ।।
(ハタヨーガプラディーピカー 2章22節)
धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिर्लौलिकी त्राटकं तथा ।
कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत् ।।
( ゲーランダ サンヒター 1章12節 )
2つの古典書によるとシャトカルマの内容は
ダウティ(धौति)、バスティ(बस्ति)、ネーティ(नेति)、トラータカ(त्राटक)、ナウリ(नौलि)、カパーラバーティ(कपालभाति)これら6つを指します。
それではここからひとつづつ確認していきましょう。
कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते ।।
(ハタヨーガプラディーピカー 2章22節)
धौतिर्वस्तिस्तथा नेतिर्लौलिकी त्राटकं तथा ।
कपालभातिश्चैतानि षट्कर्माणि समाचरेत् ।।
( ゲーランダ サンヒター 1章12節 )
2つの古典書によるとシャトカルマの内容は
ダウティ(धौति)、バスティ(बस्ति)、ネーティ(नेति)、トラータカ(त्राटक)、ナウリ(नौलि)、カパーラバーティ(कपालभाति)これら6つを指します。
それではここからひとつづつ確認していきましょう。
【1】ネーティ(नेति )
主要なネーティは2つあります。
1. ジャラ ネーティ(जलनेति)
写真の専用ポットはプラスチック製で、他には陶器、銅製などがあります。携帯用としてはプラスチック製、衛生面では陶器が適しています。銅製は錆びた時の手入れが必要になります。
ほか、ギーや油を用いたテール ネーティ(तेलनेति)
牛乳によるドゥグダ ネーティ(दुग्धनेेति )もあります。
特殊な例として、牛尿や自分の尿を用いたネーティもあるそうです。牛の尿は、プージャの最中に飲用することもあり、インドの義母もグラス一杯飲んでいますので、飲むなら鼻から入れるのも有りですね。私もプージャで飲んだので牛尿の味を知っているですが、浄化する何かがあるのは頷けます。これは話が横にそれて長くなるので、また後日お伝えしたいと思います。
2. スートラ ネーティ(सूत्रनेति)
スートラとは紐のことをいい、紐を鼻から通して口から出す行法です。ジャラネーティで清浄した後に行います。
古代は、細い綿の紐に蜜蝋をつけて硬度を高めて使用していました。現代ではカテーテルがよく使われます。
先端にギーや油などを塗り、鼻から挿入して喉元まで垂れ下がってきたところを手で引っ張り口から出します。上下に軽くしごきますが、デリケートな部分ですので、まずは通ったら十分です。 蓄膿症の人は通りづらいので、炎症しやすい食物を控え、長期的に徐々に慣らし、鼻腔内の形を徐々に整えていきます。
首から上の部分、視力、聴力、片頭痛を改善します。また、普段左右どちらかの鼻から偏って呼吸をしている人にとって左右のナーディのバランスが整います。
スートラネーティ用のゴムチューブは使用前に先端が割れていないか、破損していないかを確認します。下の写真のものは、一方が破けていますが鼻に入れる側の先端は破損していないので大丈夫です。
(前半 スートラ ネーティ/後半 ジャラ ネーティ)
【2】ダウティ(धौति)
ダウティのことをシュッディ(शुद्धि)と呼ぶこともあり、英語でクレンジングの意味です。ダウティは大別すると4種類あり、個々の行法の中にさらに分類があります。ダウティは最も行法の種類が多いです。
大別すると、
(1)アンタル ダォティ(以下a、b、c、d の4種)
(2)ダント ダォティ(以下e,f,g,h の4種)
(3)フリッダ ダォティ(以下i,j,k の4種)
(4)ムーラ ショーダン (1種類のみ)
4種の詳細を見ていきましょう。
(2)ダント ダォティ(以下e,f,g,h の4種)
(3)フリッダ ダォティ(以下i,j,k の4種)
(4)ムーラ ショーダン (1種類のみ)
4種の詳細を見ていきましょう。
1. アンタル ダウティ (अन्तर्धौति)
アンタルとは内部。アンタル ダウティとは体内の浄化を指します。
これには以下の4つの分類があります。
(a)シャンカ プラクシャーラン
(b)アグニサーラ クリヤー
(c)クンジャラ ダウティ
(d)ワータサール ダウティ
(a)シャンカ プラクシャーラン(शंख-प्रक्षालन )
胃腸の清浄を目的とした、水による浄化法。
ワーリサーラ ダウティ(वारिसार धौति )ともよびます。ワーリとはサンスクリット語で水、サーラは「タットヴァ」、つまり「本質」というような意味で、水の性質を利用して浄化することをいいます。 口から大量のぬるい塩水をゆっくり分けて飲みます。2杯飲むごとに特定のゆるいアーサナをし、最終的に16杯程飲みます。
アーサナの途中で尿意、便意があれば我慢せずに出るだけ出して、最終的に便・尿として出し切ります。この行法をする人数分だけのトイレを確保しておく必要があります。
定められたアーサナには、立姿勢で両手を上に伸ばして背伸び、ウエストねじり、側伸、腹部を床につけた状態で上半身を起こし左右にねじるポーズなどがあります。
これは消化器に適度に刺激を与えながら、隅々まで水をいきわたらせ、最終的に便や尿として排出することから、法螺貝の意味であるシャンカ(शंख)と名付けられています。
インドでは法螺貝の中に水を入れて飲むと健康に良いと信じられているのですが、一方から法螺貝に水を入れると、らせん状に水が落ちて出ていく様を表現しています。
また、街中で売られている法螺貝はコーティングを施してあるものが多いので、ツルっとした光沢の質感を思い出されることかと思いますが、本来の形状は特に内側の渦を巻いている部分は大小の凹凸があって、それが人間の腸にも例えられるようです。正しい食事をしていても腸の凸凹に食事の内容物が残って蓄積していくので、1年に1,2回するのが好ましいとされます。
この浄化法については一冊の専門書があるほどで、何日も前から事前に体のメンテナンス準備が必要です。 猛暑や極寒の季節を避け、前日は早めに夕食を済ませ、当日は日の出前にこの行法を行います。激しいアーサナや仕事はせず、2,3日ゆっくりとした生活で過ごすために日程調整をしておきます。
この浄化法については一冊の専門書があるほどで、何日も前から事前に体のメンテナンス準備が必要です。 猛暑や極寒の季節を避け、前日は早めに夕食を済ませ、当日は日の出前にこの行法を行います。激しいアーサナや仕事はせず、2,3日ゆっくりとした生活で過ごすために日程調整をしておきます。
締め付けない服を着、シャンカ プラクシャーランが終わった後、40分程シャヴァアーサナ(死体のポーズ)をし、そこからちょうど45分後に食事を摂ることが好ましいとされるため、自身で食事の準備はせず、可能なら協力者にお願いできると良いでしょう。食事は消化に優しい豆粥(キチュリー)にギーを沢山混ぜて頂きます。
また、インドの豆粥は、ムーング豆などを使用しています。
いくつかの決まり事として、シャーストラには「この行法の前に肉を食すなら死にいたることもある」と指示されています。食事は数日間は徹底して唐辛子やカフェイン、アルコールは断ち、スパイスや調理油は必要最小限の低刺激を心がけます。
(b)アグニサーラ クリヤー(अग्निसार -क्रिया)
(b)アグニサーラ クリヤー(अग्निसार -क्रिया)
ヴァフニサーラ ダォティ(वह्निसार धौति )とも呼びます。
初期の練習として、ヴァジュラーサナ(正座、金剛座)になって座り、左右の膝はできるだけ開いて座り、足の指は合わせておきます。手のひらは下にして膝に置きます。両肘は伸ばし、少し前傾姿勢になります。口を全開にして舌を出し素早く口から息を吸い吐きます。犬を真似て口からすばやく呼吸をするイメージです。リズムがとれてきたら、息を吐く際に腹筋を収縮させ、息を吸う際に腹筋を緩めます。10回から20回を1セットとします。
初期の練習が容易くできるようになったら、アグニサーラ(ヴァフニサーラ)の訓練に入ります。正座のほか、パドマーサナ(蓮華座)で行うこともできます。息を外に吐き出しジャランダラバンダの体勢で腹部の収縮と拡張を連続的に行います。息が苦しくなったらジャランダラバンダをほどきます。
この行法はジャトラーグニ ヴァルッダカ(जठराग्नि वर्द्धक)という消化の炎を強めます。便秘、ガス、肝臓、肛門の弛みなど不調を改善するほか、有り余った消化の炎は怠惰、無気力、悲壮感をかき消します。
(c)クンジャル ダウティ(कुंजल धौति)
水を使用した胃の内部までの洗浄で、1,5から2リットルの塩水を飲んで口の奥に指を入れて吐き出す方法です。
象の意味であるクンジャル(कुंजल)は、象が鼻から水を吸い上げて、一気に水を放出して水浴びするように、ヨーガの行法では何杯もの塩水を飲んで一気に吐き出し、胃の中を洗浄します。吐き出す時は喉の奥を指で押さえて吐くため、爪は短く切っておきます。最後まで吐き切れないと、余分な塩分が体内に残り、一日ぐったりするので、30分以内に素早く吐き切ります。
私ははじめてした日に、午後は身体が重く感じたり、食事中に塩味を全く受け付けない時がありました。余分な塩分がたまっていたせいか塩分を排出しやすくするためにバナナが無性に食べたくなりました。初めてするときは師匠が見守ってくれていますが、出し切った感は自分にしかわからないので、師匠が「それぐらいでいいでしょう」と言ってもまだ吐き足りない時は自分が納得できるまで出し切るぐらいの心構えが必要です。
ゲーランダーサンヒターではワマナ ダォティ (वमन धौति)とも呼ばれます。ワマナ( वमन)とは「吐く」という意味で、体内に不要な熱が滞留している時、ピッタが増悪している時や、粘液の多い体質の改善のために行います。
ハタプラディーピカーではこれをガジャカラニー(गजकरणी )と呼んでいます(2章38節)
講師の中には、この行法のことをヴィャーグラ クリヤー(vyaaghra kriya व्याघ्र क्रिया)と呼ぶ人もいます。ヴィャーグラは虎のことで、虎は食事の数時間後に吐き戻す習性があるそうです。猫と同じく草を食べて吐き出すことを指しているのかとも考えられます。ヴィャーグラ クリヤーでは食後3~4時間後に胃に残っている食事の残留を吐き出す行法をいいます。
前者のクンジャラ ダウティやガジャカラニーは、朝から何も食べずに完全に胃の中が空である状態で行う点で、ヴィャーグラ クリヤーと異なります。
胃の中に入った食事を何故吐き出す必要があるのか、それならば断食のほうが易しそうだ、という話をインドの先生に意見すると「インド人はそこがクレイジーなんだよね」とのことでした。
(d)ワータサール ダウティ(वातसार धौति )
空気を飲み込み、腸内に送り、空気そのものを消化するイメージで肛門まで排出し、胃腸を洗浄する行法。口から空気が逆流しないようにし、肛門から出して完成です。
慢性の便秘にも良いとされます。消化のためには腸内の移動を促す象徴であるワータ(風)の働きや、スペースが必要となります。
食前に行い、食後には行いません。消化力を上げ、胃酸過多の緩和と心臓を強化します。
2.ダント ダウティ(दन्त धौति)
口内や首から上の浄化法。ダント ダウティは伝統的な呼称で、シールシャ ダウティ(शीर्ष धौति)とも呼ばれています。 これは以下4つ(e,f,g,h)のダウティに分類されます。
(e) ダント ムーラ ダウティ(दन्तमूल धौति)
歯茎のマッサージや歯のブラッシング。古代はニームの木の枝が歯ブラシとして使われました。現代的なのは練歯磨きが多く使用されますが、昔ながらのハーブの粉末を愛用する人もいます。
(f) ジヴハームーラ ダウティ(जिव्हामूल धौति)ともいいます。
舌のクリーニング。
(g) カルナランドラ ダウティ(कर्णरन्ध्र धौति)
耳掃除のことですが、耳垢をとる他、耳全体、後ろ側にもオイルを塗ってマッサージを行います。大家さんから教わったことで「マスタードオイルでニンニクを2,3粒素揚げし、そのオイルを鼻の穴や耳の穴に塗っていると風邪をひかない」とのことです。臭いは強いですが、試してみると体が温まる感じがしました。
(h) カパーラランドラ ダウティ(कपालरन्ध्र धौति )
顔全体のマッサージで、額からはじます。目の周辺、こめかみ、耳周辺、首のマッサージ。
顔全体のマッサージで、額からはじます。目の周辺、こめかみ、耳周辺、首のマッサージ。
3. フリド ダウティ(हृद् धौति)
フリド は心臓を意味し、心臓、胸部の浄化のための行法です。
大別して3つあります。
大別して3つあります。
・ダンダ ダウティ( i )
・ヴァマナ ダウティ( j )
・ヴァストラ ダウティ( k )
・ヴァマナ ダウティ( j )
・ヴァストラ ダウティ( k )
(i)ダンダ ダウティ(दण्ड धौति)
グラス数杯分の水を飲んだ後で、長い太めのゴムチューブを口から挿入し、腹部の収縮運動で胃の水を逆流させる浄化法。わかりやすい動画を見つけたので拝借しました。動画の6分0秒から、古代式のダンダ ダウティも紹介していました。ウコンの茎を使って口から挿入するそうです。慣らすために、水を飲まずに食道の掃除のみをする仕方もあります。
(j)ヴァマナ ダウティ(वमन धौति)
上記のクンジャラ・クリヤーを参照。
(k)ヴァストラ ダウティ (वस्त्र धौति)
薄く細長い布を湿らせて飲み込んだあと、ゆっくりと抜き出し胃の汚れを取り去る方法。飲み込んだあとにナウリをして布をかき回すように浄化すると更に布がドロドロになって出ます。 数十センチ飲み込んで出すだけでもドロドロになって水道水だけでは布汚れが落ちないぐらいですので、布を飲めば飲むほど胃の浄化はできそうです。 ただ、時間がかかる上、インド製の目の粗い布ガーゼを30分ほど入れていると消化が始まり、布がうまく取り出せないこともあります。「口から抜き出す時に布が切れてしまったら、そのまま放っておけば大腸通って出るから大丈夫よ」と言っていたインド人の講師もいました。
4. ムーラ ショーダン(मूलशोधन)
肛門の洗浄法。これについては分類なし。
ムーラショーダンはダウティに含まず、後術の【4】バスティ(बस्ति)の中で説明されてあるものもあります。
ムーラ ショーダンの方法は【4】のバスティ(बस्ति)で述べます。
【3】ラウリキー/ナウリ(लौलिकी/ नौलि)
ワータ(風)の働きを活用して、腹部の筋肉を動かしながら腹部全体のマッサージを行う行法です。消化器官の強化、特に小腸に刺激を与え活発にし、食欲を増します。起床後排泄を済ませてから空腹の状態で行います。
成長期の子供、妊婦、高血圧、ヘルニア、潰瘍の患者、手術後は禁忌。
ナウリのために事前にアグニサーラ クリヤー(अग्निसार क्रिया)とウッディヤーナ クリヤー(उड्डियान क्रिया)の習得が必要です。
それができるようになってから、ナウリ クリヤ(नौलि क्रिया )に取り組みます。ナウリクリヤーには4段階があります。
1.マッディヤ ナウリ(मध्य नौलि)
立姿勢で前かがみになり、息を吐いてからジャランダラバンダで腹部を凹まし、中央部に筋力を集中させます。
立姿勢で前かがみになり、息を吐いてからジャランダラバンダで腹部を凹まし、中央部に筋力を集中させます。
2.ワーマ ナウリ(वाम नौलि)
腹部の左側に腹筋を寄せます。左手は左膝の上に置き、右手は右膝から離しておくことで重心と意識を左側に向けやすくなり、腹筋を左に収縮させやすくなります。
3.ダクシナ ナウリ(दक्षिण नौलि )
腹部の右側に腹筋を寄せます。右手は右膝の上に置き、左手は左膝から離しておくことで重心と意識を右側に向けやすくなり、腹筋を右に収縮させやすくなります。
4.ナウリ サンチャーラン(नौलि संचालन)
別称、ブラフマ ナウリ(ब्रह्म नौलि)、ヒンディ語で「ウダル カー マンタン (उदर का मन्थन)”腹部の攪拌”」ともいいます。
【4】バスティ(बस्ति)
大腸,、肛門、直腸の洗浄と強化を目的とする浄化法。
主に、以下の(1)と(2)のほか、(3)のムーラ ショーダンをバスティに含む解説も見られます。
(1)ジャラ ヴァスティ(जल वस्ति)
腰まで浸かれる水深のある川などで立ち姿勢になり、上半身を前へ傾け両手を膝についた状態で、肛門から水を吸い上げる。ウッディヤーナ・バンダとナウリを行い大腸に水をため、しばらくたってから排出する。
(2)スタラ ヴァスティ(स्थल वस्ति)
パシュチモーッターナーサナの姿勢で肛門から空気を吸い上げ、25回アシュヴィニームドラーをしたあとで排出します。アシュヴィニームドラーは馬が肛門を収縮したり緩めたりするのを繰り返す様に、肛門の収縮と拡張を繰り返すムドラーです。
(3)ムーラ ショーダン(मूलशोधन)
肛門の浄化。便秘と痔の改善。
ウコン(ターメリック)の塊を肛門から挿入する。ウコンの塊が入手できなければ選択肢として、中指、人差し指にターメリックパウダーを入れる方法でもよい。10回ほど時計回りに回した後、ウコンの根、または指を肛門から引き出す。ウコンは抗菌や血液を浄化する作用があります。
ウコン。生姜に似ていますが、香りはターメリックです。
ムーラショーダンは別称
•ムーラ ダウティ(मूल धौति)
•ガネーシャ クリヤー(गनेश क्रिया)
•チャクリー カルマー(चक्री कर्मा )
•ガネーシャ クリヤー(गनेश क्रिया)
•チャクリー カルマー(चक्री कर्मा )
とも言います。
【5】カパーラバーティ(कपालभाति)
カパーラとは頭蓋骨、頭という意味で、脳内を活性化させるために行う行法です。呼吸法としてのカパーラバーティで頭がすっきりした経験をされたことでしょう。
このカパーラバーティにはジャラクラマ(जलक्रम)とワートクラマ ( वात्क्रम)に2分類されます。ジャラクラマは水を用いた行法で、ワートクラマは風を用いた行法です。
・ジャラクラマ(जलक्रम)には2種類あります。
ひとつはシタクラマ カパーラバーティ(शितक्रम कपालभाति) で、これは口から塩水を飲み、鼻から出す浄化法です。
もうひとつのビュトクラマ カパーラバーティ(व्युत्क्रम कपालभाति)は鼻から塩水を入れて口から吐き出す浄化法です。
・ワートクラマ ( वात्क्रम)
ワートクラマ カパーラバーティ(वात्क्रम कपालभाति)は呼吸法で行うカパーラバーティのことを指します。
【6】トラータカ(त्राटक)
・バヒラ トラータカ बहिर त्राटक
バヒラは外部のという意味で、視界に映る花や星、像、ロウソクの炎など、ひとつの焦点に視線を定め、瞬きを極力せずに涙がでるほど見続けます。集中力と目の浄化のための行法です。 月、水晶玉、鏡はトラータカに不向きとされます。太陽に集中するならば日中は避け日の入り時刻にします。
トラータカの対象を1つ決めたら他のものに変えないようにし、変えた場合には、新しい対象物に心を同化する初期の状態にリセットしなくてはいけません。
目の浄化、目力、記憶力、忍耐力を高め、無気力、倦怠感、不眠症、緊張、神経過敏を改善します。また、眉間のアージュニャチャクラが活性化するので、空腹時かつ瞑想前に行うことが好ましいとされます。
・アンタラ トラータカ अंतर त्राटक
目を閉じてチャクラやそれに関するビージャマントラ、神の名前や姿、また自身の心に集中します。バヒラトラータカと比べ、対象がより微細になります。
また、バヒラ トラータカをしたあとで目を閉じて、さっきまで凝視していたものを鮮明に導き出す方法もアンタラ トラータカです。